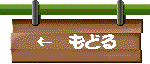喘ぎながら辿り着いた石墨山の頂上は、明るい早春の光に満ちあふれていた。東を望むと五代の別れのピ−クと西の冠岳の間から、石鎚山の本峰が残雪を輝かせながらこちらを覗いているのが見えた。さて、ゆっくりお弁当でも・・・と言いたいところだが、今日の目的は、南斜面を下って「赤鬼法性院」という行者のミイラを探索することにある。その話を「面河村誌」から拾ってみることにしょう。
「・・・昔、石墨山の南の直瀬村に赤鬼法性院とよばれる行者が住んでいた。ある日、ふと見ると、大木のような大蛇がうさぎを一飲みにしようとしている。彼はとっさに持っていた鎌で蛇を突き刺し、か弱いうさぎを助けてやった。その夜、ただならぬ気配にふと眼を醒ますと、先ほどの大蛇がすでに体に巻き付いていて法性院を飲み込もうとしている。行者の妻はうろたえ悲鳴をあげるばかり。万事休す、と思われたが、法性院は、少しも慌てず「包丁、包丁。」と叫んで、妻からかろうじて包丁を受け取るや、一刀のもとに大蛇を切り刻んでしまったという。また、あるときは、大雨で直瀬村に落ちてくる大石を、母と二人で受け止めて村を救ったという。このように身の丈7尺に余る、剛胆不敵、怪力の大男は村人の信頼を得て崇められたと伝えられる。そんな彼も死期を悟って山に入り、鐘を叩き経文を唱えながら静かに入定したという。彼の身を案じた村人が登ってみると、石墨山南面八合目の岩陰に静かに俯せて死んでいるのを見つけた。そこで、その岩陰にお堂を建て、ミイラのままお祭りして「石墨大権現」と称した。今も岩陰のお堂には、法性院の巨大な白骨が納められ、邪心の者が触れると、一天にわかにかき曇り大雨が降ると伝えられている・・・」
以上が「石墨山伝説」の概要だ。伝説ではあるが、寛保年間(西暦1741年頃)に編纂された「久万山手鑑」という書物を見ると、杣野村の山伏として「法性院」の名が記されているとのことで今から250年前に実在していた人物であることは間違いなく、とても現実的な話に思えてくる。では、肝心のお堂の位置はどこだろう?位置を明記した文献はみあたらないが、2万5000分図(石墨山)をみると南斜面八合目とおぼしきあたりに岩場の印が認められる。直瀬村からの道もあって、ここに違いないと思われた。そして、後日入手した昭和初期の5万分図(松山南部)を見て、この予想が正しいことの確証を得た。なんと、その岩場に重ねて、神社を示す鳥居マ−クが記されていたからだ。
山行にあたってもう一度、北川先生編集の「いしづち」をひもとく。昭和15年5月の石墨山登山記事だ。「・・・中腹に来ると崖下の窪地に小さなお宮がある。その向こう側には小さなお堂の中に伝説の行者のバラバラになった骨が納めてあって、その前に「行者入仏之処」と記した木札が立ててある。人間の頭としては少し小さ過ぎるようだ・・・」
今もこのままお堂に納められているのだろうか?江戸時代に流行した即身成仏を祀った場所は四国でもところどころ見かけるが、ほとんどは入定した場所に石塔などが立てられているのみで、直接、即身仏を拝めるところはない。出羽三山には遠く及ばないが、もし、そのままの状態であれば極めて貴重な修験遺跡ということになるだろう。発見の期待が大きく膨らむ。
そして、その日は来た。平成10年3月29日。お天気にも恵まれ初夏の陽気に、気を良くしながら南面の笹原を駆け下りてゆく。道はないに等しいが、意気揚々と皆の眼も輝いている。次第にスズタケと灌木の混じるブッシュとなるが、尾根を外さないように強引に下ってゆく。200mほど下って、緩斜面の杉林に到着する頃、ようやく疲労を覚えた女性軍が前進を止めてしまった。どう考えてもミイラがあるような場所ではないのだ。猜疑の眼が一斉に我々に向けられる。仕方なく男性軍が手分けして付近を探索する。あたりは一面の植林地で、すこし下るとそれらしい岩場もあったが、お堂やミイラは、結局発見することができなかった。ただ、木々を透かして、法性院も見たであろう直瀬村が、春霞に深く沈んでいるのが印象的であった。
失望しながら登り返す斜面は本当につらく苦しかったが、「伝説は伝説としてこのままそっと置いておくのがよいのかもしれない。見つけなくてよかったのかもしれない。」と慰めてくれる声にようやく心も安らぎ、登るにつれて次第に遠のいてゆく南の山林に向かって静かに合掌した。
(写真:石墨山上より俯瞰する直瀬村)